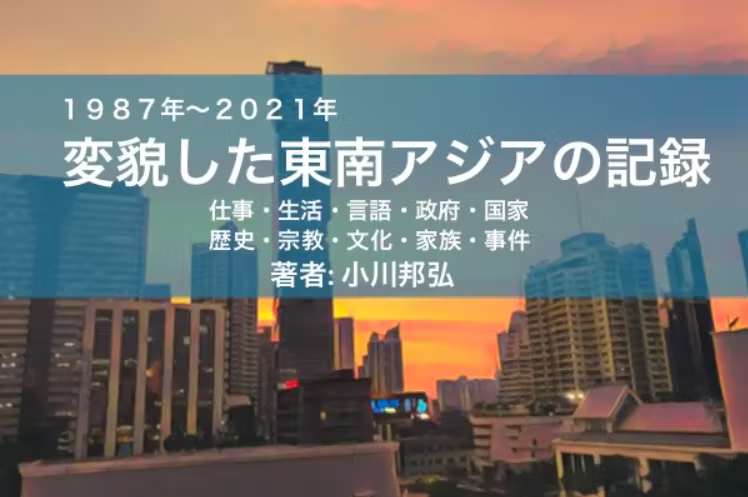タイの政権は、カネで国家権力を買ったタクシン・シナワット時代が長く続き、その権力奪取の過程での汚職が追及され犯罪者となった彼は結果的に国外逃亡し、彼はそのまま海外で流転生活(といっても有り余る資産をお持ちなので、あちこちの国で豪邸暮らしをできる身の上だが)を送っている。その後政権は対抗馬の民主党に移譲されたが、タクシンは海外に身を置きながらありとあらゆる手で政権を操り、政治・行政に全く縁の無かった実妹、インラック・シナワットを農民票の買収により首相に据えた。逃亡中の犯罪者である彼が、あろうことか法律を捻じ曲げてでもと政権復帰を画策し、法常識では「超法規的措置」とされている恩赦を「立法化」しようと試みた。そして農閑期の農民に日当を支払いバンコクの中心にある大交差点を占拠させるなどの無謀な圧力をかけたのだが、やがて暴徒と化したタクシン勢力下のデモ隊の一部が武器を使用し、またいくつかのショッピングセンターやビルに放火するに至り、これを軍隊が制圧し、暫定軍事政権により、吹き荒れた政変の嵐は沈静化したのである。
そして現在、その軍事政権はインラック元首相に対し、上記の買収工作に伴って行った政府によるコメ買取政策で国家財政に莫大な損失を与えたという罪で訴えを起こしている。つまり権力を乱用し国庫負担で政権維持を図っていたということだ。これは早晩、有罪となり巨額の損害賠償も求められることは確実と言われている。
その状況下でインラック前首相は、これも兄の指示なのか似た者兄妹なのか、一時は検察庁幹部を逆起訴するなどという暴挙に出たこともある。いったいどこの国で「容疑者が検察官を訴える」ことが許されるのだろう。この様に法律も裁判制度も一切無視した悪あがきを続けているのである。
さらに最近になって、欧州議会がインラック前首相を「個人的に」招待した、と報じられた。元より欧米の政権からは。「選挙によらない手段で成立した軍事政権」は全てステレオタイプ式に「悪」と批判されており、その批判を利用したタクシン派が前首相の国外逃亡を画策し欧州議会に働きかけたもの、と見られている。外国で今まさに裁かれようとしている容疑者である前首相を公人ではなく“個人的に”招待するという矛盾、またこの招待自体を内政干渉とは云わないのであろうか?